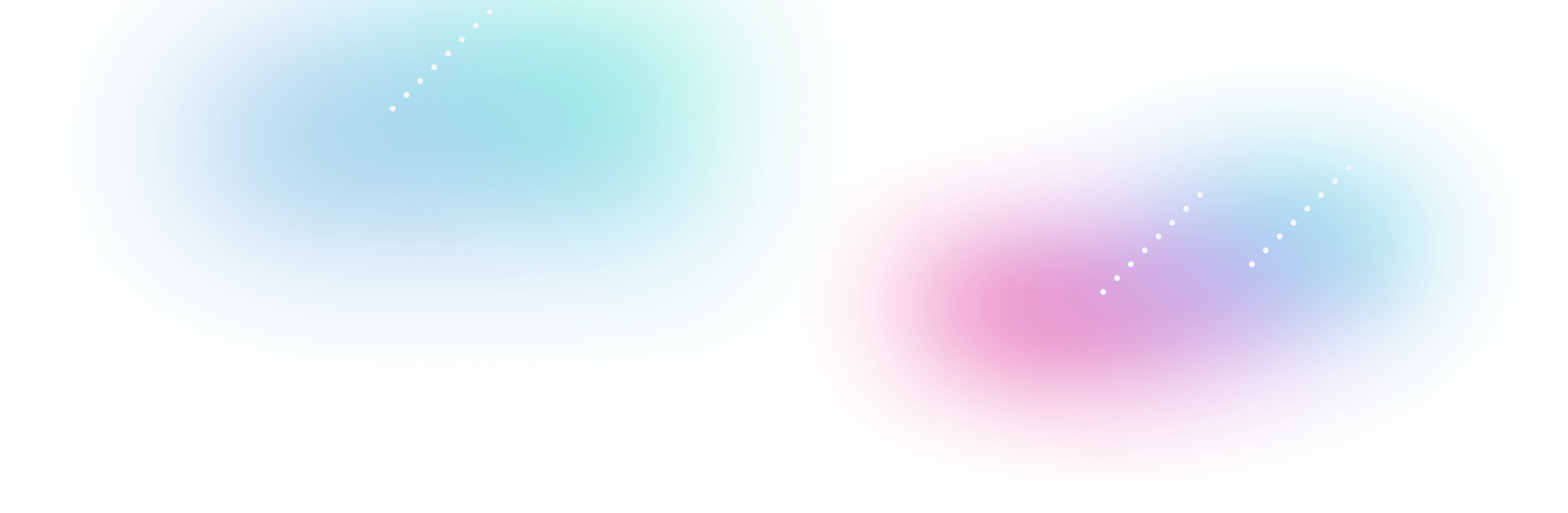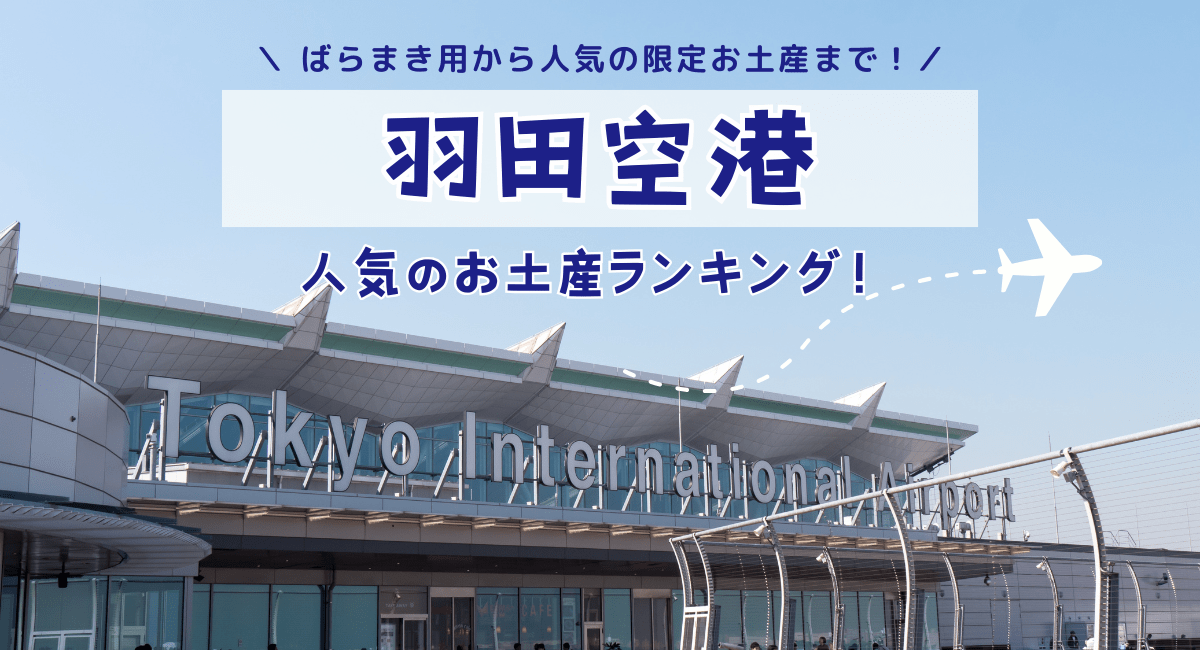地域と人が共に育つ場所!NPO法人北海道エコビレッジの持続可能な取り組み

NPO法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト 代表 坂本 純科さんのインタビュー

画像引用元:NPO法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト
長年、野菜や花を育ててきましたが、最近では土づくりの面白さやガーデンデザインの魅力に改めて目覚めています。
目次
introduction

画像引用元:NPO法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト
北海道余市町に拠点を構える「NPO法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト」は、持続可能な社会の実現を目指して、環境に優しい暮らしを実践しながら、その価値を多くの人に伝え続けています。
都会の喧騒を離れ、「自分たちの手で作り、使い、循環させる」ことの大切さを学び、持続可能なライフスタイルを実際に体験できるのが大きな魅力です。定期的に ワークショップや研修プログラム が行われており、農業やガーデニング、DIY、環境教育など、実践的なスキルを学ぶことができます。これらの活動を通じて、「NPO法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト」は、地域と共に協力しながら持続可能な未来を築くための具体的な取り組みを続けています。
今回は、代表の坂本 純科さんに、「NPO法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト」の持続可能な取り組みについてお話を伺いました。
自然と共に生きるエコビレッジでの暮らしと学び——NPO法人北海道エコビレッジの推進プロジェクト

画像引用元:NPO法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト
– 北海道エコビレッジ推進プロジェクトでは、どのような活動を行っているのですか?
坂本さん:
私たちは、多様な国々からくるボランティアとともに共同生活をしながら、6haの敷地で野菜や果物を育てています。また、エネルギーや住まいを手作りする技術を身に着け、それらを地域で分かち合う暮らし方を目指しています。
– エコビレッジの暮らしを通じて、どのようなことを学ぶことができるのでしょうか?
坂本さん:
エコビレッジでは、リアルな暮らしの場を通して「サステナブルな暮らしと社会」という抽象的なテーマを、多くの人に実体験をもって学ぶ場を提供しています。
北海道でエコビレッジを広める理由とは?

画像引用元:NPO法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト公式Facebook
– 北海道エコビレッジ推進プロジェクトを始めたきっかけを教えてください。
坂本さん:
退職後、ヨーロッパのエコビレッジを訪問・滞在する旅を経て、自給的な生活をするコミュニティがその場を解放して教育や交流のプログラムを作っていること、それが地域の交流人口を増やし、循環や経済活性につながっていることに感銘を受けました。
– なぜ北海道の余市でこの活動をしようと考えたのですか?
坂本さん:
ヨーロッパで見たエコビレッジの仕組みや考え方を、過疎化が進む北海道の町村でも実践できないかと思い、余市で活動を始めました。
NPO法人北海道エコビレッジ推進プロジェクトのSDGsへの取り組み

画像引用元:NPO法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト
– 北海道エコビレッジ推進プロジェクトでは、SDGsのどの目標に特に力を入れて取り組んでいますか?
坂本さん:
私たちはすべてのSDGsのゴールに取り組んでいると言っていいと思います。特に力を入れているのは「食とエネルギーの自給による環境負荷の低減」「異年代、異文化、異分野の人びとによってつくる多様なパートナーシップ」「より人間らしく、ウェルビーイングな社会」です。
– それらの取り組みを、どのような形で実践しているのですか?
坂本さん:
これらの取り組みは、いずれも小さなスケールではありますが、外から訪ねてくる方々にエコビレッジの暮らしを通して持続可能な社会のモデルを体験してもらえるようになっています。
地域の魅力を活かした観光と環境保全の両立

画像引用元:NPO法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト
– 観光振興と環境保全を両立させるために、どのような取り組みをされていますか?
坂本さん:
地域の歴史や自然、産業など、もともとその土地にある資源や、町の人が大切にしているものを中心に、外部から訪れる人たちと共に、それらを守り育てていくような交流事業を目指しています。
農業体験を通じて生まれる長期的なつながり

画像引用元:NPO法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト公式Facebook
– 農業体験やイベントを企画する際に、大切にしていることはありますか?
坂本さん:
私たちは、100人が1時間滞在する観光ではなく、1人が100日滞在するような交流事業を理想としています。
– 具体的にどのような形で、参加者とのつながりを深めているのでしょうか?
坂本さん:
繁忙期には農家の作業を手伝うボランティアとして来てくれる方も多くいます。また、私たちが送る農産物を、まるで実家から届くギフトのように楽しみにしてくださるファンの方々もいます。
– 農業体験を通じて、どのような関係を築いていきたいと考えていますか?
坂本さん:
私たちは、お客様にサービスを提供しているのではなく、長期的に互いに支え合う仲間づくりをしていると考えています。
農業体験がつなぐ「ふるさと」のような関係

画像引用元:NPO法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト公式Instagram
– 農業体験に参加した方々から、どのようなつながりが生まれていますか?
坂本さん:
修学旅行で農業体験をした高校生が、卒業後にボランティアとして戻ってきてくれることがあります。
– 訪問後も地域と関わりを持ち続ける方もいるのでしょうか?
坂本さん:
はい。例えば、近所のリンゴ農家の手伝いをした学生が、後日「台風で落ちたリンゴを買いたい」と電話をくれたことがあります。
– こうした体験を通じて、訪問者と地域の間にどのような関係が生まれるのでしょうか?
坂本さん:
まるで「ふるさとの親戚」のような関係が生まれることがあります。
世界とつながる「余市ピースワイン」への挑戦

画像引用元:NPO法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト
– 北海道エコビレッジ推進プロジェクトでは、ワインづくりに取り組んでいると伺いました。どのような活動をされているのでしょうか?
坂本さん:
私たちは、21品種のワインブドウを育て、世界の多様な国々の人々とともにワインづくりに取り組んでいます。
– 現在、ワインづくりはどのような段階にあるのでしょうか?
坂本さん:
まだ試作の段階ですが、近い将来「余市ピースワイン」として世に出ることを楽しみにしています。
– このプロジェクトを通じて、どのようなつながりが生まれていますか?
坂本さん:
栽培のプロセスには、大学のゼミや企業研修、さらには紛争中の国からやってきた人たちとの交流など、さまざまなストーリーが生まれました。

画像引用元:NPO法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト公式Facebook
NPO法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト・会社概要
| 社名 | NPO法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト |
| お問合せ先 | ◯余市エコカレッジ事務局 〒046-0002 北海道余市郡余市町登町1863 TEL/FAX:0135-22-6666 ◯札幌事務局 〒064-0959 北海道札幌市中央区宮ケ丘2丁目1-1-303 FAX:011-640-8422 |
| 代表者 | 坂本 純科 |
| 事業内容 | イベント・講座開催/ワークキャンプ/グループ研修・視察受け入れ/大学や研究機関と連携した教育プログラム/農業体験プログラム |
| 公式サイト | https://ecovillage.site/ |
自然と人がつながる場所NPO法人北海道エコビレッジ推進プロジェクトのまとめ

画像引用元:NPO法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト公式Facebook
北海道エコビレッジ推進プロジェクトは、ただの「エコな暮らし」を実践する場ではなく、人と自然、地域と世界が交わる場所として成長を続けています。農業やエネルギーの自給を目指しながら、ワインブドウの栽培を通じた国際交流や、訪問者と地域の人々が長く関わり続ける関係づくりなど、ここには「持続可能な未来」へのヒントがたくさん詰まっています。
訪れる人にとって、ここでの時間は単なる体験ではなく、新しい価値観に出会うきっかけになることでしょう。
人気記事
人気・おすすめタグ
関連記事
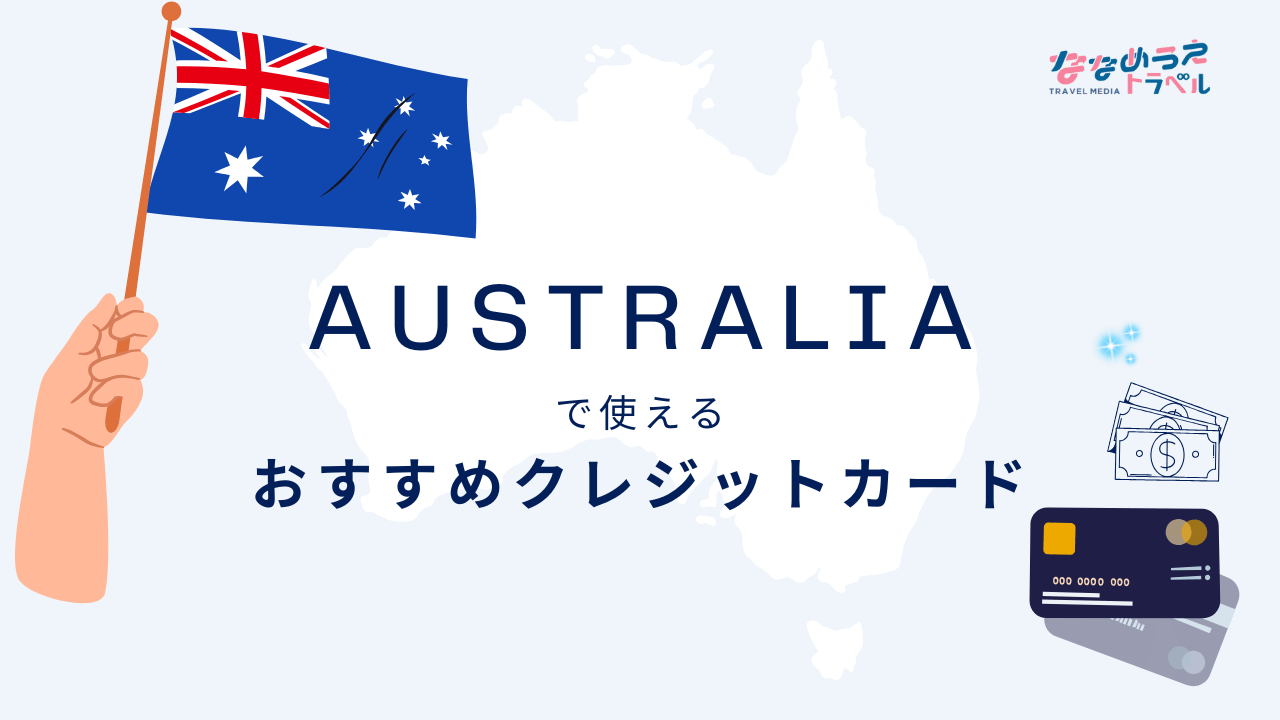
オーストラリア旅行で使えるおすすめのクレジットカード7選🇦🇺手数料や使える国際ブランドで比較

海外旅行におすすめの最強クレジットカードランキング!手数料を比較してお得な1枚を紹介
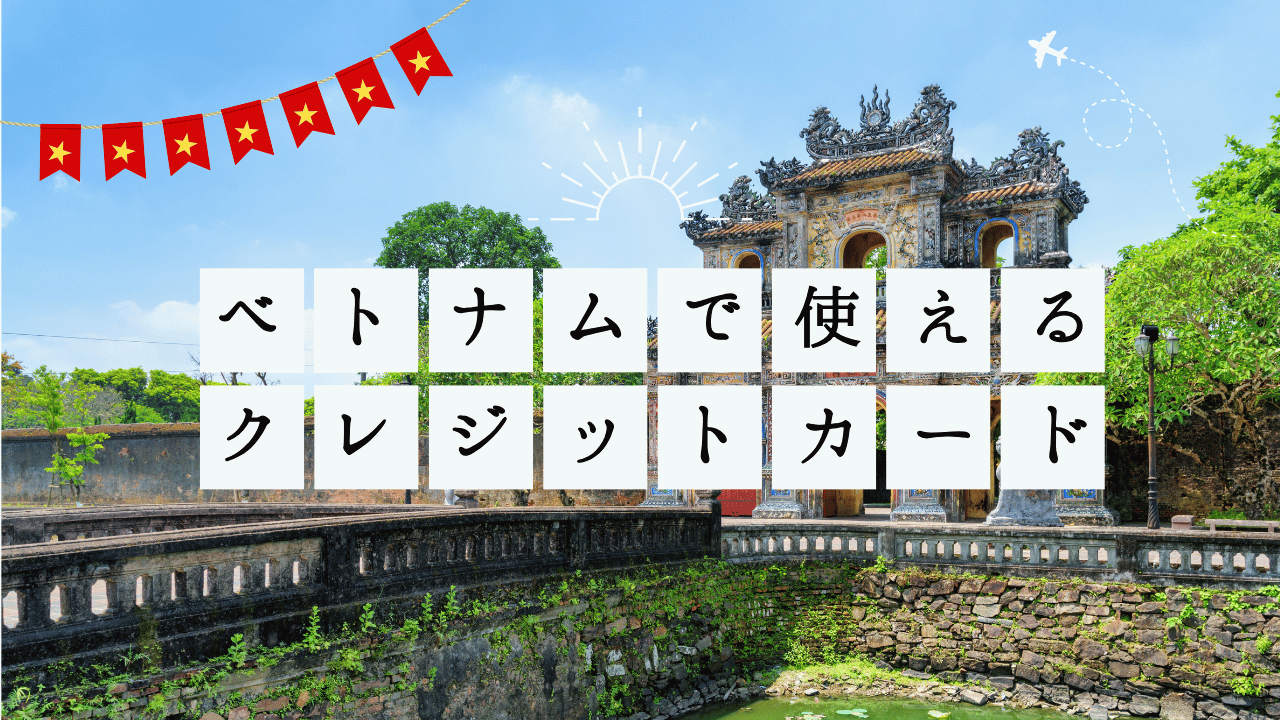
ベトナムで使えるおすすめのクレジットカード6選🇻🇳使ってみた感想を元に普及率や安全性を解説
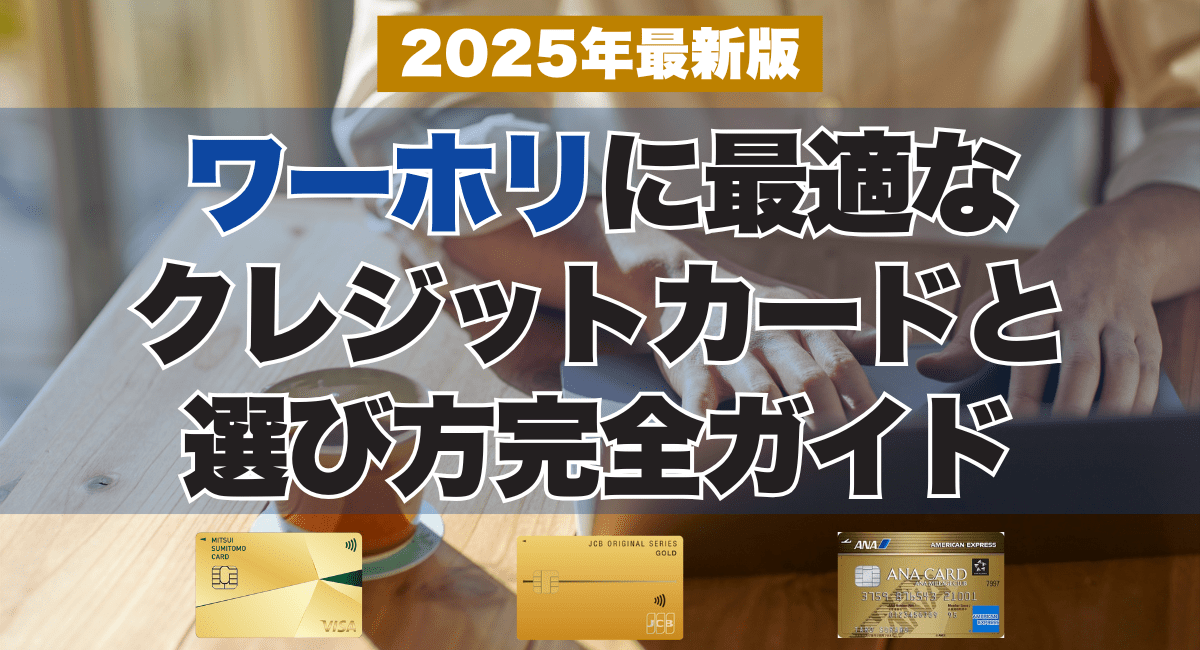
ワーホリにおすすめのクレジットカード!メリット・デメリットや選び方の完全ガイド

ANAマイルの貯め方に裏技はある?有効期限の決まり方や陸マイラーのコツまで解説

韓国旅行に必要な持ちもの・アプリを渡韓歴30回以上の私が紹介!”あればよかった”を防げる持ち物紹介
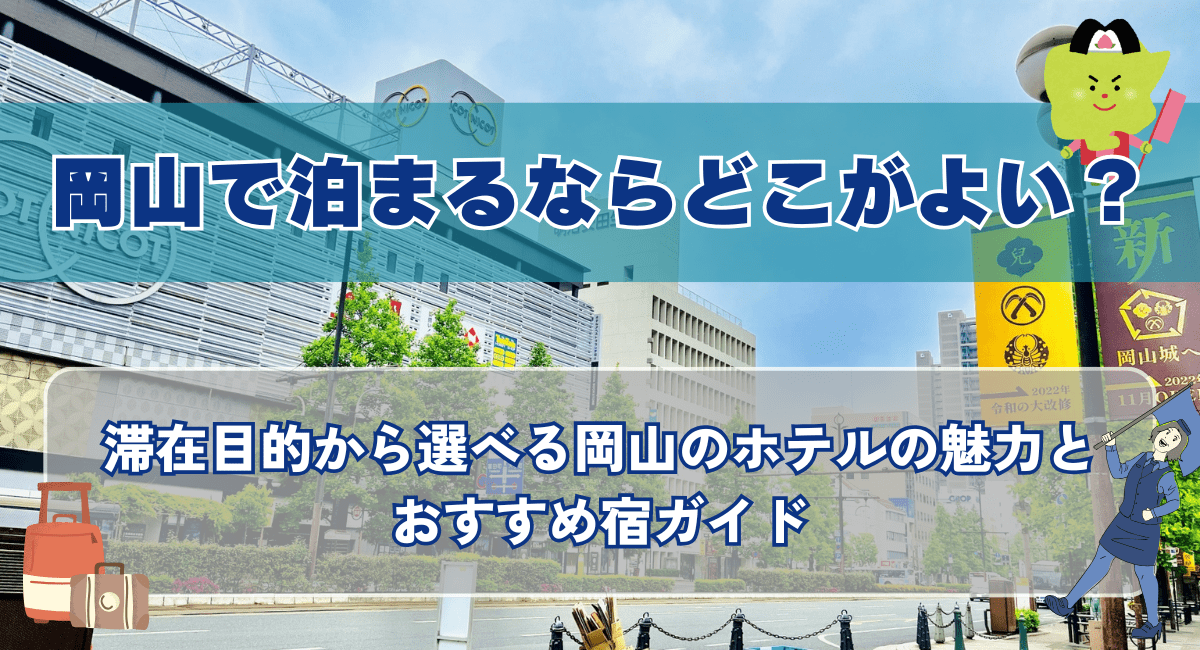
岡山で泊まるならどこがよい?滞在目的から選べる岡山のホテルの魅力とおすすめ宿ガイド

台湾で使えるおすすめクレジットカード8選!キャッシュレス事情や国際ブランドの普及率を解説
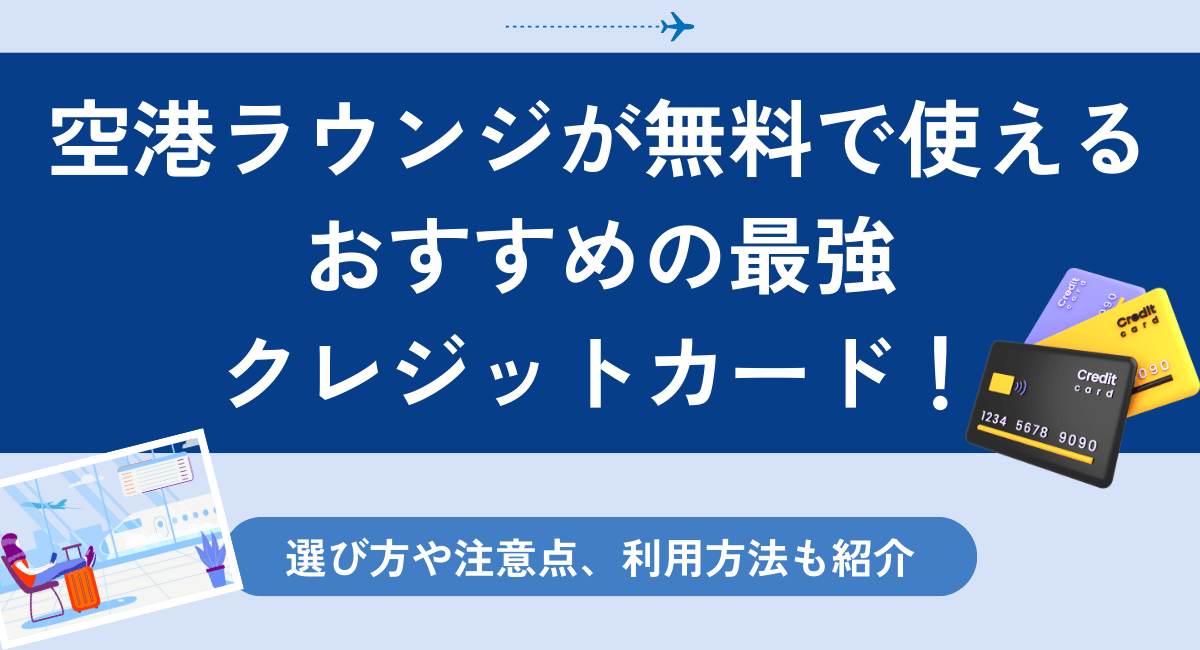
海外の空港ラウンジが使えるおすすめの最強クレジットカード!無料で作る方法や注意点、利用方法も解説
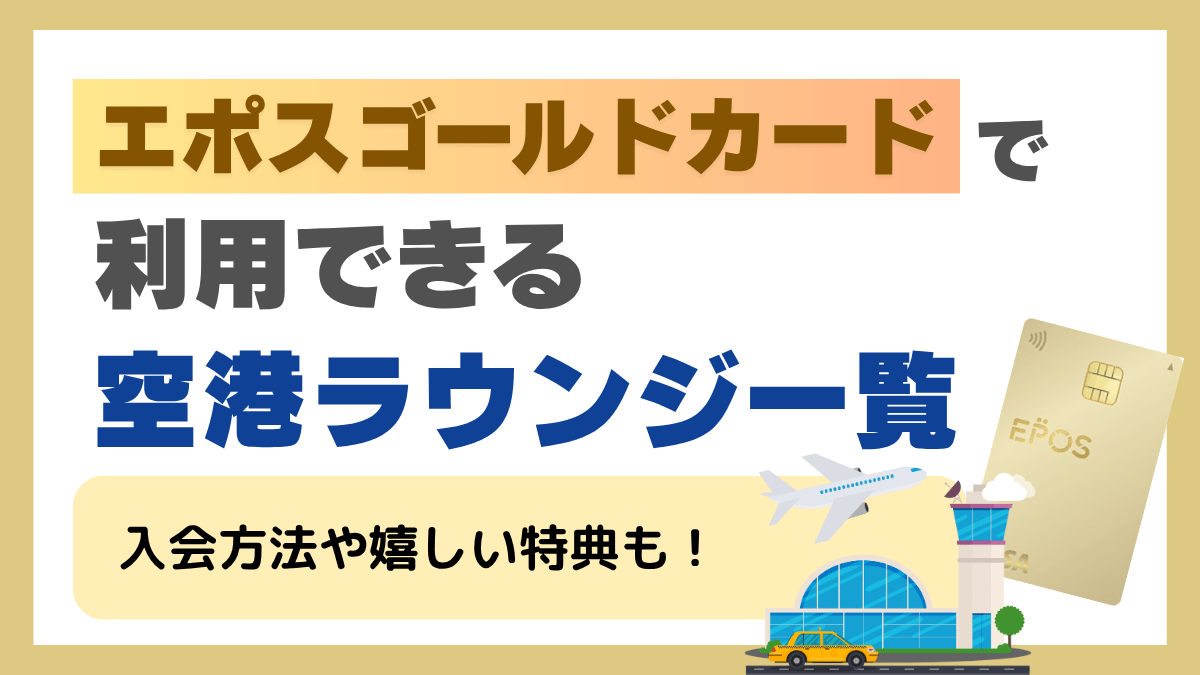
エポスゴールドカードで利用できる空港ラウンジとは?羽田・成田で使えるラウンジとそのほかの旅行関連特典について解説
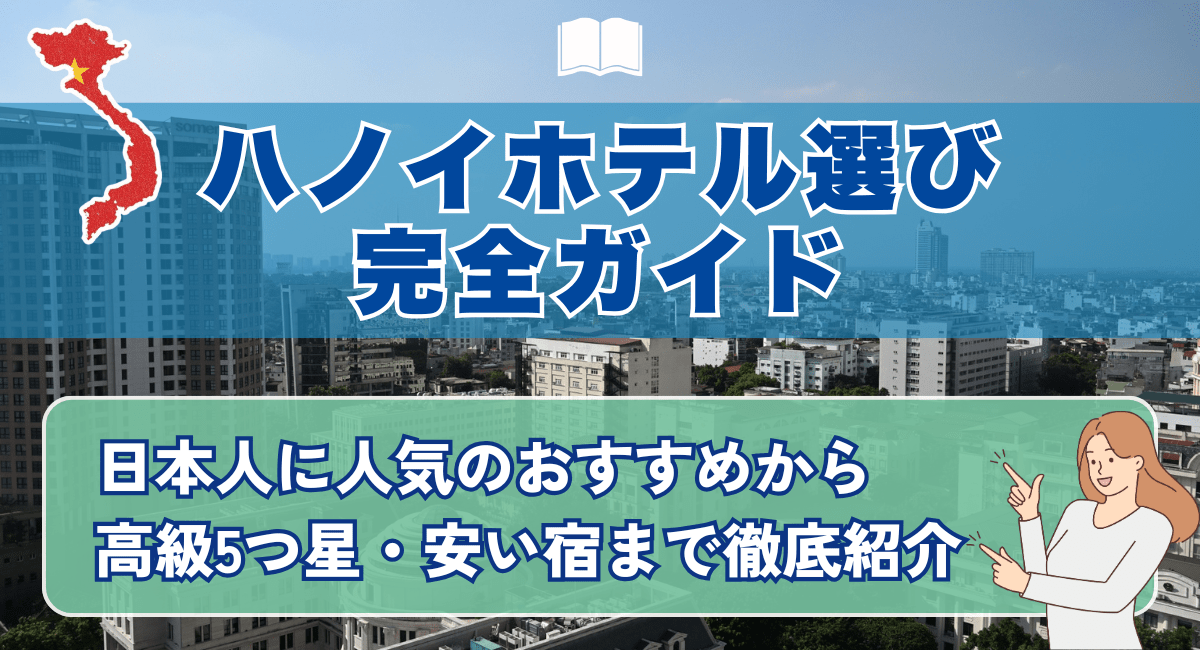
ハノイホテル選び完全ガイド|日本人に人気のおすすめから高級5つ星・安い宿まで徹底紹介

【2026最新】PayPayカードの新規入会キャンペーンは今がお得!メリット・デメリットやチャージ方法について解説